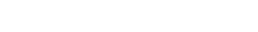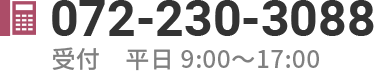相続コラム相続に関する様々なご相談を
コラムにまとめました
遺留分とは? 相続人が最低限貰える財産について
相続が起こった際に、亡くなった方が遺言書で全財産を他人に譲ると書いていた場合、
法定相続人(前回の記事を参照)は、全く遺産を貰えないのでしょうか?
法定相続人が全く貰えないことを回避するために、「遺留分」という制度の存在を
聞いたことがある方も多いと思います。
今回は遺留分についてお伝えしたいと思います。
「遺留分」とは?
遺留分とは、
“一定の相続人”のために、“法律上必ず留保されなければならない相続財産の割合”
をいいます。
“一定の相続人”とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、父母等直系尊属)になります。
兄弟姉妹は法定相続人ですが、遺留分はありません。
つまり、兄弟姉妹に相続財産をあげたくない場合は、
全財産を第三者か他の相続人に譲る旨を遺言で記載しておけば良いことになります。
次に、「法律上必ず留保されなければならない相続財産の割合」は、
父母等の直系尊属のみが相続人のときは、故人の財産の3分の1、
それ以外の場合は、故人の財産の2分の1になります。
遺留分を有する権利を持つ相続人が複数人いる時は、上記の遺留分の割合に、
それぞれの法定相続分の率をかけたものが、相続人一人の遺留分になります。
・・・ちょっと難しくなってきました。
具体的な事例に当てはめて、遺留分の額を見ていくことにします。
相続人が配偶者と子供2人の場合
故人の財産が1200万円で、
法定相続人が配偶者Aさんと、子供Bさん、子供Cさんだった場合を見ていきましょう。
まず、法定相続人が父母等の直系尊属のみが相続人“以外”の場合にあたりますので、
全体の遺留分の率は2分の1となり、
法定相続人に法律上必ず留保されなければならない相続財産の割合は、
1200万円に全体の遺留分の率(1/2)をかけた600万円になります。
配偶者Aさんの法定相続分の率は2分の1なので、
全体の遺留分600万円にAさんの法定相続分の率(1/2)をかけた300万円が
配偶者Aさんの遺留分となります。
次に子供BさんとCさん2人合わせた法定相続分の率は2分の1なので、
一人分の法定相続分の率は4分の1になります。
全体の遺留分600万円にBさんの法定相続分の率(1/4)をかけた150万円が
Bさんの遺留分となります。
CさんもBさんと同様の計算式で150万になります。
もし遺言書に全財産1200万円を第三者に譲ると書いてあっても、
Aさんは300万円、BさんとCさんは各150万円を
遺留分として取得をする権利があると主張することができます。
相続人が父母のみの場合
故人の財産が1200万円で、
法定相続人が父Aさんと、母Bさんだった場合を見ていきましょう。
まず、法定相続人が“父母等の直系尊属のみが相続人”の場合にあたりますので、
全体の遺留分の率は3分の1となり、
法定相続人に法律上必ず留保されなければならない相続財産の割合は、
1200万円に全体の遺留分の率(1/3)をかけた400万円になります。
全体の遺留分400万円にAさんの法定相続分の率(1/2)をかけた200万円が
Aさんの遺留分となります。BさんもAさんと同様の計算式で200万になります。
谷口司法書士事務所では、相続が発生した際のご相談、
遺言や遺産分割協議に基づく不動産の名義変更等の手続きのご依頼を承っています。
是非、ご相談ください。
堺市中区新家町765番地11
谷口司法書士事務所
TEL:072-230-3088