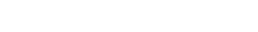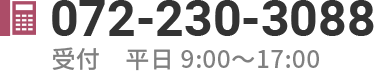相続コラム相続に関する様々なご相談を
コラムにまとめました
遺言書作成のご相談は司法書士へ。残された家族のために。
最近は「終活」という言葉を聞くことが増えてきました。
「終活」とは、自分の死と向き合い、これまでの人生を振り返ったり、残される家族のために何ができるかを考えたり、
と、人生の最期を迎えるにあたっておこなう様々な準備のことをいいます。
終活の一環として、「遺言書」を書いた方、また「遺言書」を書こうかと検討されている方も
沢山いらっしゃると思います。
テレビドラマ等では、「タンスの引き出しの中から遺言書が見つかった」なんていうシーンを
結構見たことがありますが、遺言書は正しく書かないと無効になってしまうことはご存知でしょうか?
今回は遺言書の種類と書き方についてお伝えします。
遺言には「普通方式」と「特別方式」の2種類がある
遺言には「普通方式」と「特別方式」があります。
「特別方式」は、病気で死亡の危急に迫った人が書いたり、遭難中の船の中で書いたり、と、
緊急時や特殊なケースの場合に書く遺言書になります。
ですので、一般的には、事前に用意する遺言書は、「普通方式」の遺言書になります。
「普通方式」の遺言書は3種類
「普通方式」の遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
1)自筆証書遺言
自筆証書遺言に求められる要件は、
“遺言者が遺言書の「全文」「日付」「氏名」を「自書」し、これに「押印」すること”
です。これらのうち一つでも欠けると、遺言は無効になります。
例えば、日付を「○年○月」と年月しか書いていなかったり、「○年○月吉日」と書いていたりした場合は、
日付が特定できないので無効になります。
パソコンで文章を作成しプリントアウトしたものは、遺言者本人が作成していても「自書」には当たりません。
これに対して、カーボン紙を使用して複写の方法で記載されていて、
遺言者の筆跡が確認できる場合は、自書に当たりますので有効です。
押印は、拇印でも指印でも構いませんし、実印である必要もありません。
自筆証書遺言は、公証役場での手続がないので費用がかからず、書き直しや修正が自由に
出来る点にメリットがあります。しかし一方で、書き方を間違えると無効になったり、
亡くなった後に遺言書が発見されなかったりするデメリットがあります。
2)公正証書遺言
公正証書遺言は、公正証書によってする遺言のことをいいます。
公正証書の原本は公証人役場で原本が保管されますので、紛失したり偽造や変造されたりすることがありません。
また、自筆証書遺言には「検認(※)」という手続きが必要ですが、公正証書遺言には検認は不要です。
(※)検認とは、家庭裁判所がする遺言書が正しい形式で書かれているかをチェックする手続です。自筆証書遺言の場合は、検認手続を経ないと財産の相続手続きができないので、検認のない遺言書では、預金口座も不動産の登記名義も変更することができません。
公正証書遺言は、以下の流れで作成します。
①遺言者と司法書士が事前に遺言の内容について相談
②印鑑証明書等の必要書類を準備
③司法書士が文案を作成
④司法書士が公証人と文案を調整
⑤遺言者が文案を確認、文案を確定
⑥公証人役場で遺言書に署名押印
公正証書遺言は公証役場で作成するので、書式が整っていない等の理由で無効になることはなく、
また、遺言書の原本は公証役場で保管して貰えるので、安全かつ確実に遺言を残すことができます。
一方で、公証役場での作成になるので自筆証書遺言よりは手続に時間がかかり、費用もかかります。
3)秘密証書遺言
秘密証書遺言は、封印した遺言書に公証人の公証を受ける遺言のことをいいます。
遺言の内容は秘密にしておきたいけれども、遺言の存在自体は明らかにしておきたい場合等に利用されます。
秘密証書遺言を作成するには、まず署名・押印した遺言書を作成します。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言のように自書が要求されていないので、パソコンで作成して
プリントアウトしたものも有効な遺言書として取り扱われます。
次に、作成した遺言書を封筒にいれて、遺言書に押印した判子と同じ判子で封印します。
その後、封印した遺言書を公証役場に提出します。
秘密証書遺言は、公証役場に支払う費用を抑えることはできますが、
内容を公証人に見て貰わないため、方式や内容に不備があると無効になる可能性があります。
谷口司法書士事務所では、開業以来大変多くの方から遺言書作成のご相談・ご依頼を承っています。
是非、ご相談ください。
堺市中区新家町765番地11
谷口司法書士事務所
TEL:072-230-3088